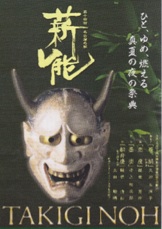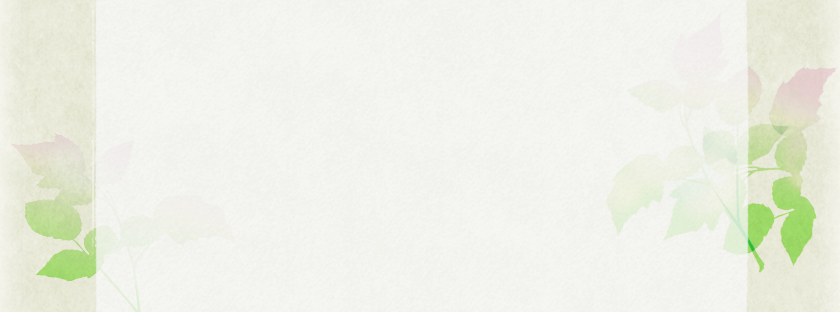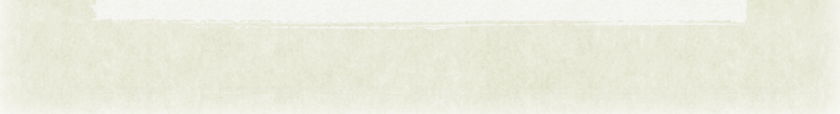7月の暑い盛り、薪能を見に行った。応募してみたら抽選に当たった。二席いただくも興味のある友人はそういない。薪能は夏場の夜に、舞台の周囲にかがり火を焚いて、その中で演じる。「薪の宴の能」の意味とのこと.
今回の薪能の演目は
舞囃子 「巻絹」
仕舞 「忠度」
狂言 「墨塗」
能 「船弁慶」
狂言: 「黒墨」は田舎大名が帰省する際に京中で親しくなった女性に別れの挨拶をするため訪問する。女性が泣き、うその涙を流す。召使が水を墨に置き換え、墨を目の下につけた女性を・・・・・見て・・・笑いが・・・。といった内容で、静かな情景の中での笑いを誘う。
能: 「船弁慶」は 義経が頼朝に追われるようになり、静御前を都に戻すことになった。静御前は悲しみの舞を舞う。 次に、逃れるため船で義経が海上に出ると、激しい波が押し寄せる。西国で滅亡した平知盛の亡霊が長刃をもって義経に襲い掛かる。弁慶が数珠で祈祷し、祈られた亡霊が次第に遠ざかり、波がおさまる。という内容。
前シテは静御前 後シテ-平知盛の亡霊 小方-源義経 ワキ-武蔵坊弁慶 ワキツレ -従者 の6人が出演。 舞台後方には囃子方、後見、地謡、の14人の方々が並んだ。
狭い舞台の中での表現、大きめの枠で、船を表現、それに、義経・弁慶達が乗り込み、先頭がオールをこぐ。ゆっくりとした舞、せりふ、お囃子の中でこれらを表現していくことの面白さも感じる。
暑い中、面をつけ、何キロあるのだろう、あの衣装を着て舞うのは大変なことと思う。ストーリーをしっかり知ってから見ないと何が何だか解からない。能は4回目になるが、やっと面白さが見えてきた。初めて、やっと、狂言の面白さ、能が表現する内容がわかったような気がする。ダンスに比べれば動きの少ない舞であるので、年齢を重ねないと、時間にゆとりがないと感じられないのかもしれない。能の面や衣装が素晴らしい、日本の伝統芸能と確信している、長く保存してほしい。
能は14世紀も半ば、観阿弥(かんあみ)、世阿弥(ぜあみ)という親子の役者によって完成される。父の観阿弥は、拍子中心の「曲舞(くせまい)」という新しい音楽を生み出し、息子の世阿弥は、歌や舞を中心にする優美なものに変えた。世阿弥は死後の世界を重視し、幽霊が登場して自分の過去を舞で表現、そして成仏するという話が多いようだ。
調べると、薪能の起源は平安時代中期、奈良の興福寺で催されたものが最初だという。興福寺では、今年5月15日、16日に薪能が行われた。薪御能(たきぎおのう)と呼ぶ。
時間にゆとりができたら、能を是非見ていただきたい。A.M.