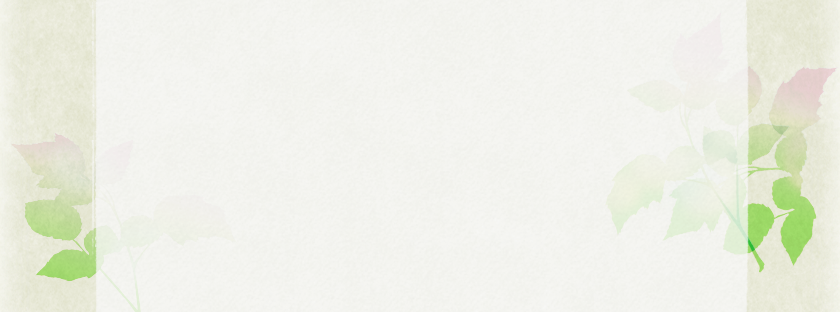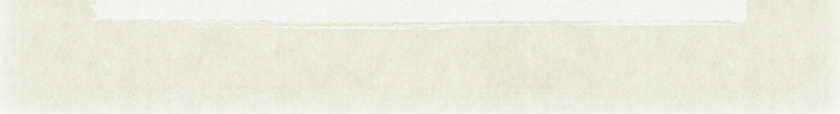縁結びの神・福の神として有名な「出雲大社」、明治時代初期まで杵築大社と呼ばれていました。主祭神は「大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)」で、「古事記」に記される国譲り神話には、大国主大神が高天原の天照大神(あまてらすおおみかみ)に国を譲り、その時に造営された天日隅宮(あまのひすみのみや)が出雲大社の始まりといわれています。
伊勢神宮は天照大御神を祭っています。昨年平成25年に式年遷宮が行われましたが、出雲大社でも式年遷宮が行われました。出雲大社では60年に1回行われます。第1回目は659年斉明天皇の頃だとか。平成20年4月に御神体を拝殿に移し工事が開始されました。こちらは新しい社を建てるのではなく、造営当時のものをできるだけ残し、後世に伝えるため、痛んだ個所や、腐朽した部材の取り替えや修繕にとどめられました。それでも5年の歳月を費やし、平成25年5月に遷宮の儀式「本殿遷座祭」が斎行されました。天照大御神の息子を先祖とする千家尊祐(せんげたかまさ)宮司が祝詞を奏上し、神職120人余りの行列が、ご神体とともに出発、境内を時計回りに遷御。本殿前へ、そしてご神体が遷座されました。
本殿は高さ25m、日本一の大社造りで、現在のものは江戸時代に建て替えられたものだそうです。9本の柱があり、入口は本殿の真ん中ではなく右側からはいり、ご神体はその奥の部屋に西を向いて遷座されています。
ところで出雲大社の本殿は飛鳥時代ごろまで高さ96mもあったそうです。これは27階のビルに相当します。このご本殿は平安時代末ごろの平面図「金輪御造営差図」が残っています。信じがたいのですが、平成12年本殿前の地下から巨大な本殿跡の一部、3本の柱を1本に束ね直径3mの柱の根元部分が発見されました。これによって巨大本殿の実在が高まっているのです。
私は以前、出雲大社を訪れたことがあります。大きなしめ縄のある拝殿へ、お参りをし、おみくじを引いて帰りました、ところが本殿はその奥にあります、拝殿を本殿と間違えたのです。本殿をお参りしていないことがくやまれます。みなさんぜひ訪れたら、本殿と発掘された柱をぜひ見てください。そして飛鳥時代の本殿を想像してみてください。
出雲大社は神話のロマンがいっぱいあるかもしれません。A.M.
写真は、出雲大社HPより(手前が拝殿、奥が御本殿になります)